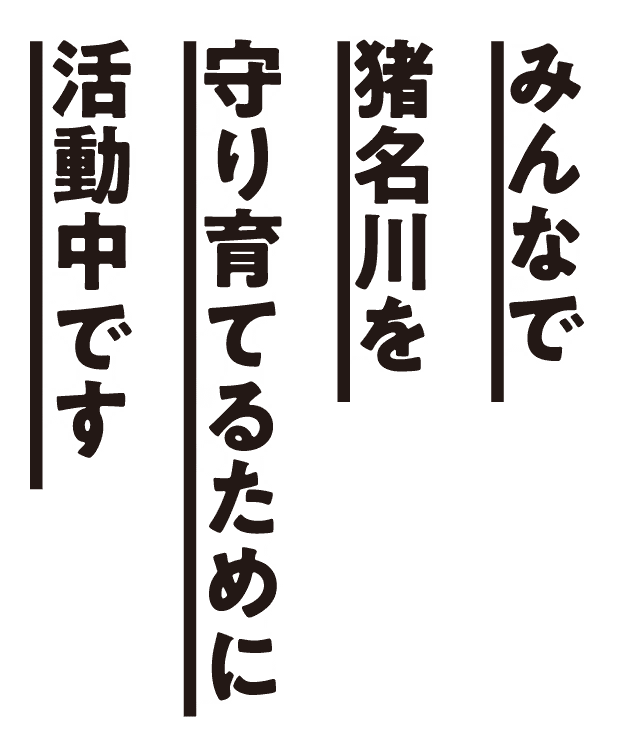活動レポート
活動レポート
第2回河川レンジャー交流会
「河川レンジャー」の制度は、淀川水系河川整備計画に位置づけられており、淀川水系の淀川・木津川上流・琵琶湖・猪名川の4河川事務所ごとに各河川レンジャーが様々な活動を行っています。この河川レンジャー活動のより一層の推進を図るため、昨年度に続き、河川レンジャーの交流会が開催されました。
今回は、淀川管内河川レンジャー事務局の山口氏の進行で、流域治水をテーマとした活動体験や、意見交換のワークショップが行われました。猪名川からは、原口河川レンジャー、水谷河川レンジャー、田中河川レンジャー協力員の3名が参加し、他の河川レンジャーの方々と交流しました。
- 日時令和7年1月12日(日曜日) 10:00~15:00
- 参加者淀川管内河川レンジャー 11名
木津川上流管内河川レンジャー 1名
琵琶湖河川レンジャー 2名
猪名川河川レンジャー 3名(原口R、水谷R、田中R協力員)
河川管理者、事務局 - 内容・河川レンジャー活動体験(歴史散策、浸水歩行体験)
・ワークショップ①活動にひと工夫を加えよう!
・ワークショップ②活動を深めよう! - 場所淀川流域センター
- 主催淀川管内河川レンジャー、淀川河川事務所

【アウトブレイク・自己紹介】
淀川管内河川レンジャー事務局の進行で、アイスブレイクと自己紹介ゲームからスタートしました。相手を見つけて互いに自己紹介し、ジャンケンに勝った方が質問をして相手が答えるゲームで、参加者同士が楽しく交流し、まずはお互いの距離を縮めました。


【活動体験① 浸水地歩行キット】
淀川管内河川レンジャーの日頃の活動体験として、まずは「浸水地歩行キット」の紹介を受けました。本キットは持ち運びができる水防災の体験施設として設計・作製したもので、現在は誰でも運用できるマニュアルも整備し、出前講座や地域の防災イベントで活用されているそうです。
実際に屋外で設営を見学すると、各パーツと防水シートの組み立てにより、短時間でキットが完成しました。そこに水を貯めて、実際の浸水時と同様にゴミや泥を混ぜると準備完了です。参加者が順番に浸水地歩行を体験し、浸水時の歩きにくさ、足元の見えにくさ等が実感できることを確認しました。


【活動体験② 歴史探訪ウォーク】
浸水歩行キットに水を貯める約40分の間に、周辺の歴史探訪ウォークを体験しました。
はじめに淀川の堤防道路横に建てられている「明治18年洪水碑」の説明を受け、淀川堤防が約180メートルにわたって決壊し広範囲が水没した歴史についてお聞きしました。続いて周辺を歩きながら、旧堤防跡や洪水の歴史が分かる地形、合同樋門跡等について説明を受けました。猪名川河川レンジャーで行っている歴史・防災の活動と似ている部分もあり、とても興味深く感じられました。


【ワークショップ①活動にひと工夫を加えよう!】
室内に戻り、4テーブルに分かれてワークショップを行いました。一人ひとりが付箋に「河川や活動への要望・課題」と「それに対して行った活動の工夫」を書いて台紙に貼ってから、テーブル毎に1人1分で内容を発表し、お互いの河川レンジャー活動の状況について情報交換しました。
【ワークショップ②活動を深めよう!】
午後は、環境保全、歴史文化、人づくり、河川利用の4テーブルに分かれての意見交換を2セット行い、意見交換後、各テーブルの座長より成果を発表しました。河川は違っていても活動の内容や課題は似通った部分が多く、どのテーブルも様々な話で盛り上がっていました。
●環境保全
主に外来生物対策について話し合いが行われ、外来生物は各河川で分布拡大しており重大な課題であること、いずれの河川でも外来生物問題には苦慮していることが共有されました。しかし、外来生物(特に動物)の駆除は非常に困難であるため、最終的には、まずは子供たちに川の楽しさや川の生物の魅力を伝えることが河川レンジャー活動として最も重要ではないか、と取りまとめられました。
●歴史文化
原口レンジャーが座長をつとめ、活動に際しての情報収集方法に関して意見交換が行われました。現地調査、図書館・公民館等での情報収集のほか、観光ガイド等も地域の歴史を知る手段になるとの意見があり、今後の活動に役立つ情報交換になりました。
●人づくり
活動を次世代につなげる方法や、地域との連携方法について意見交換が行われました。活動を通して子供に伝えていくことが大切との意見が多く、事例として、淀川のジュニア河川レンジャー(河川レンジャーのプログラムを子供に体験してもらう活動)が紹介されました。また、学校や地域の活動に河川レンジャーが入り込むためには、地域に顔を出し、河川レンジャーを知ってもらうことが重要であるとの意見もありました。
●河川利用
淀川の河川レンジャーが計画している親水利用拠点づくりの方法について意見交換が行われ、継続的にその場所を使う人が中心となった草刈りや、河川協力団体との連携による管理等のアイデアが出されました。




長時間の交流会でしたが、参加者はまだまだ話し足りない、といった様子でした。猪名川の河川レンジャーも、活動への意欲がより一層高まったと思います。